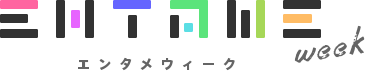魚の中でも異質な形をしているコバンザメ。力の強い者にすり寄り、そのおこぼれにあずかる者のことを比喩的に「コバンザメ」と呼んだりしますが、では一体コバンザメはどんな魚なのでしょうか。今回はコバンザメの生態とコバンザメにまつわる書籍を紹介します。
コバンザメはどんな魚?
はじめにコバンザメはサメの仲間ではありません。学術的にはスズキ目コバンザメ科に属する魚で、分類的にはスズキの仲間になります。
頭の吸盤の形状が小判に似ていることから「小判鮫」と名付けられました。
英語でもSharksucker(shark=サメsucker=吸盤)という名前がつけられています。
広告の後にも続きます
体長は70~100cmほどの大きさです。コバンザメは3属8種類存在していますが、それぞれの種類によって、くっつく相手である「宿主」が異なるそうです。
コバンザメの宿主はサメ、カジキ、ウミガメ、イルカ、マンボウなどの大型の生物がいます。イルカがジャンプするのはコバンザメがついているのがわずらわしいので、振り落とすためであるという説もあるそうです。時に船の船底にくっつくこともあります。
コバンザメの稚魚は吸盤ができるまでは自ら餌を探さなければならないため、他の魚の死んだ皮膚や体の表面についた寄生虫を食べることが多く、サンゴ礁などでは、「掃除屋」としての役割を担うことが多いのです。
コバンザメはどこに生息しているの?
太平洋東部、大西洋北東部をのぞく全世界の暖海、地中海に生息し、日本だと北海道~九州の日本海・東シナ海・太平洋、屋久島、琉球列島というほぼ全国の海で見ることができます。 宿主から離れて単独での遊泳、回遊もあります。
コバンザメがくっつくメリットは?
2022年11月19日