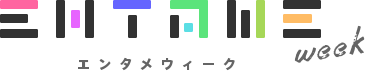日本は、1978年に平均寿命が世界一を記録して以降、長寿大国となっている。その一方で高齢化が進み、「老老介護」などの問題が課題だ。「老老介護」とは65歳以上の高齢者を65歳以上の高齢者が介護している状態のことを指すが、介護はする側も、される側も負担が大きいため、将来のための「介護予防」に注目が高まっている。
そこで、「いつまでも歩き続けて住み慣れた自宅で元気に暮らす」ことを実現するため、従来の介護サービスに、科学的アプローチ「オーダーメイド・フィットネス」を取り入れたリハビリ型デイサービス「ARFIT(以下、アルフィット)」の代表竹内洋司氏に、介護やデイサービスの最新情報についてお話を伺った。
「老後を自宅で過ごす」はどれくらい現実的か?

「令和4年版高齢社会白書」によると、介護保険制度における要介護又は要支援の認定を受けた人は、令和元年度で655.8万人に達しており、平成21年度からの10年間で186.2万人も増えている。
介護サービスには、大きく分けて「居宅サービス」と「施設サービス」とがあり、専門の介護者が訪問してケアしてくれるものから利用者が通所するもの、施設に入所するものなど様々だ。
中でも、施設に入居するのではなく、施設に通うことで入浴、排せつ、食事などのサポートや、機能訓練を日帰りで受けられるのが、通所型の施設「デイサービス」。通い型なので、利用者はいつまでも住み慣れた自宅で生活することができるというメリットがあるが、自宅での身の回りのことは、自分でするか、介護者に頼む必要がある。自宅での介護者は同居している人が54.4%で、その主な内訳は、配偶者が23.8%、子どもが20.7%、子どもの配偶者が7.5%だそうだ(「令和4年版高齢社会白書」より)。老後を自宅で過ごすというのは、考えているほど簡単なことではないのが実情だ。
「科学×介護」によるオーダーメイドの最新ケア
 オンライン取材でお話を伺った、アルフィットを運営する株式会社INSEACの代表竹内洋司氏
オンライン取材でお話を伺った、アルフィットを運営する株式会社INSEACの代表竹内洋司氏広告の後にも続きます
介護の現状を見ると、暗い気持ちになるかもしれない。しかし、要支援・要介護と言ってもその程度はさまざま。たとえば介護のレベルは、要支援1~2、要介護1~5と7つの段階がある。できるだけ早い段階で適切な介護サービスで介入すれば、要介護の段階が上がるのを防ぐこと、遅らせることは可能なのだそうだ。
そんな中、何歳になっても人生をアクティブに楽しむための「ライブケア」という新しい概念の介護予防サービスを提案しているのがデイサービス「アルフィット」だ。アルフィットでは、
1.科学的根拠に基づいた自重型の筋力トレーニング
2.データで運動成果を見える化
3.運動と栄養の両面からのサポート
と、3つのアプローチから高齢者がいつまでも歩き続けられるための健康づくりをサポートし、利用者が住み慣れた自宅で元気で暮らせることを目指している。
「アルフィットのご利用者様の中には、最初は杖をついていた方が、アルフィットで筋力トレーニングなどの運動を継続した結果、杖を使わずに歩けるようになったケースも多く見られています。これは科学的にも証明されていることですが、筋肉は年齢に関係なく、80歳になっても90歳になっても、正しいやり方でトレーニングをすれば強化できます。アルフィットではご利用者の方々へ、筋力アップ等に伴う歩行機能の維持・改善という成果を提供することで、住み慣れた自宅でいつまでも元気に暮らしていただくことを目指しています」(竹内氏)
この3つのアプローチの科学的根拠について、一つひとつ竹内氏に解説してもらった。
科学的根拠に基づいたマシーンを使わない自重型の筋力トレーニング