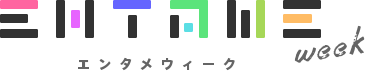さらに問題を複雑化させているのが、PvE Co-opモードがダウンロードコンテンツには含まれない点だ。同モードには、「ワイプ(メジャーアップデートの際に行われるデータリセット)」の概念がなく、『Escape from Tarkov』の世界観をより気軽に楽しめる新要素として期待が寄せられていた。であるだけに、(「今後リリースされるすべてのダウンロードコンテンツのアクセス権の付与」という)文言上はプレイできるはずだった「Edge of Darkness Limited Edition」の購入者たちは、寝耳に水の“権利失効”に驚きを隠せなかったのだろう。当然ながら、このような仕様にも多くの批判の声が寄せられている。
当初は毅然とした対応を貫いていた公式だったが、騒動の拡大を受け、態度を軟化。4月28日には、旧最上位版の購入者にPvE Co-opモードを無料開放することを決めている。想定外だったであろう猛烈な批判を浴び、リリースからの7年で構築したユーザーとの関係に大きな亀裂を残した今回の炎上。開発・発売元であるBattlestate Gamesには今後、信頼回復のための行動が求められていくことになる。
■問題の根本は、開発・発売元の見通しの甘さに
世間を賑わしている『Escape from Tarkov』新版の騒動。ここから考えられるのは、パッケージ買い切り型のタイトルを長期運営していくことの難しさだ。おそらく一連の動向のなかでBattlestate Gamesが目指していたのは、開発やサービス提供の期間が長く続くほど肥大していくコストの回収と利益の最大化だろう。旧最上位版である「Edge of Darkness Limited Edition」の販売終了、より高価格である新版「The Unheard Edition」の登場、訴求力の高い特典の流用といった事実から、そのような思惑は容易に推察できる。
『Escape from Tarkov』は上述のとおり、買い切り型のパッケージとして展開されてきたため、ゲーム内アイテムによってユーザーに課金を促すマネタイズモデルとは異なり、追加での売上獲得が難しかったと考えられる。そのため、苦肉の策として今回のような方法での目的の達成を考えたのではないだろうか。
広告の後にも続きます
しかしながら、ユーザーからすると、文言の意味する範囲を再定義することで新たな支払いを要求する、ある意味で詐欺まがいの手法のように映ってしまった面がある。半永久的にサービスを享受できるとパッケージを購入したにもかかわらず、実質的にはそこから権利が取り上げられたわけであるから、過激な批判も致し方ない反応である。
一方、追加での売上獲得が見込めない状況では、開発・発売元はサービスの継続、コンテンツの充実を考えづらくなってしまう。「魅力的な素材やアイディアがあったとしても、やがては尻すぼみ的にサービスを終焉させるほかない」。カルチャー目線で考えると、その事実は少し寂しくもある。もし騒動の論点がサービスの継続/コンテンツの充実であったなら、批判するユーザーが多いという現状の分布とは異なり、「追加で料金を払うから、魅力的なタイトルであり続けてほしい」「サービス終了となっても構わないから、追加で料金は払いたくない」の2つの派閥が生まれていたのではないか。現時点から振り返ると、パッケージ買い切り型のタイトルとして『Escape from Tarkov』を展開したこと、重要な補給線であるダウンロードコンテンツをパッケージの特典に盛り込んでしまったことが、マネタイズの難しさという問題を引き起こしているとも言える。
オンラインマルチプレイを前提とするゲームは、CS機で展開されるパッケージ買い切り型タイトルのなかにも多くある。これらもまた『Escape from Tarkov』と同様に、アップデートやコンテンツの追加を繰り返しているが、ダウンロードコンテンツの販売などにより、長期にわたる運営を実現している。また、一部がプラットフォーマーによるファーストパーティータイトルである点も見逃せない。CS機においては、オンラインマルチプレイを楽しむためにパッケージ購入代とは別に用意されている月額料金を支払うモデルが一般的である。こうした回収が開発費やサーバー代に割り当てられている面もあるのだろう。
つまり、ことPCプラットフォームにおいては、オンラインサービスの料金をユーザーに課するのが難しいという特性上、基本プレイ無料・アイテム課金型で展開する、もしくは、(買い切り型パッケージならば)ダウンロードコンテンツを資金回収の手段として残しておくというのが、マネタイズの定石となるのではないか。なかには『FINAL FANTASY XIV』のように、パッケージ購入代のほかにプレイ権のための月額料金を徴収するタイトルもあるが、このような例は稀だ。広く支持され、長期の運営を実現しているタイトルの大半が、上述のどちらかの手法を採用している。
今回の『Escape from Tarkov』新版の騒動はつまるところ、(リリース時のマネタイズモデルの選択、ダウンロードコンテンツのアクセス権をめぐる動向、後出しじゃんけん的なPay to Win要素など、諸々を含め)Battlestate Gamesの見通しの甘さが引き起こした災禍だったと言えるのではないだろうか。
既存ユーザーにとっても、今後参入する可能性がある新規ユーザーにとっても、結果的にマイナスなプロモーションとなってしまった『Escape from Tarkov』新版の発売。同タイトルが今後どのような道筋をたどるのか。その動向に注目したい。
(文=結木千尋)