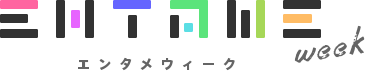コミュニケーションにおけるストレスとはどういうもの?

社内でコミュニケーションストレスが発生する原因

判断基準の曖昧さ
コミュニケーションストレスが生じる1つ目の要因が、判断基準の曖昧さです。働き方の多様化に伴い、自主性に重きを置く企業も増えています。しかしながら、社員は企業やマネージャーが設定した基準をもとに、是非の判断をしていることは忘れてはいけません。この基準が、実際に業務を行う社員へ適切に伝わっているかが重要です。
また少し極端な例ではありますが、「できるだけ早く仕上げてね」という指示もストレッサーになりえる言動です。とくに近年普及したビジネスチャットツールは、気軽なコミュニケーションが図れるものの、手軽さゆえ業務指示も簡素で省略されやすいです。
こういった判断基準を確認できない環境は、社内のコミュニケーションストレスを増幅させてしまう大きな要因となります。
配慮が足りない言動
少し抽象的な表現ではありますが、配慮が足りない言動もストレッサーになりえる要因の1つです。社員の多くが「マネージャーからの指示が唐突」「話しが終わる前に上司が話し始める」「伝えた状況を疑われる」といった事象にストレスを感じています。
伝え方によってストレスが生じると考えられがちですが、話し始めるタイミングや話の聞き方がストレッサーになることも少なくありません。
コミュニケーションストレスの改善テクニック

自己主張することを許可する
意外に思われるかもしれませんが、コミュニケーションストレスの軽減には自己主張が効果的であるとされています。たとえばあなたがマネージャーであれば、ストレスに敏感になりすぎる社員に配慮し、自己主張を行える環境づくりをおこなってみましょう。
ただし、自己主張が「アサーティブ・コミュニケーション」であることが重要です。アサーティブ・コミュニケーションとは、相手の意見を尊重しながら行う意思疎通を意味します。コミュニケーションにおける自己主張は双方向なものであり、決して一方的に話したいことを話すだけの自己主張はコミュニケーションではありません。自己主張の環境づくりとセットで、双方向にてコミュニケーションを行う意識をメンバーに共有しましょう。
アサーティブ・コミュニケーションといったコミュニケーションスキルは、鍛えておくことで非常に役立ちます。コミュニケーション能力の鍛え方は下記でご紹介していますので、ぜひご参考ください。
お互いを理解する文化を作る
お互いを理解することも、コミュニケーションストレスを軽減する手段の1つです。冒頭で触れたように、自分の頭で理解できないことが心理的ストレスの根本原因です。職場においては、お互いを理解できていないような距離感のある人間関係に、曖昧な指示といった事象が重なることで心理的なストレスが大きくなるケースも少なくありません。
そして、人に関心をもつ文化を作ることは、曖昧さの解消に役立ちます。「できる限り早くしてほしい」という指示でも、「Aさんはせっかちな人だから今日中だな」といった形で咀嚼でき、心理的なストレスが生まれにくくなるのです。
メンバー間の相互理解は多少のコミュニケーションコストがかかるものの、円滑な業務進行に欠かせない要素でもあるため、取り入れるべきと言えます。
上司との関係性を変える
企業の文化にもよりますが、上司との関係性を変えることもコミュニケーションストレスを軽減する方法です。「1on1の時間を設け、マネージャーは聞き役に徹する」といった取り組みを始めている企業も少なくありません。
ただし、マネージャーを始めとした管理者は、「社員からの相談を待つスタンス」を大切にしましょう。コミュニケーションストレスが増えていることは事実ですが、ストレスを感じていない社員も少なくはありません。希望者に1on1の場を与えることで、相談しやすい雰囲気を作り、上司との関係性を変化させることができます。