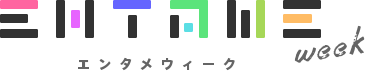原発事故に係る膨大な費用はどのように対処されているのか。「国(政府)」が今後とるべき方針とは?「原発」「福島原発事故」に関わる関連法規や豊富な判例を読み解くことで、「電力自由化」=資本主義の本質に迫る。※本記事は、森田章氏の書籍『電力の自由化と原子力発電』(幻冬舎ルネッサンス)より、一部抜粋・編集したものです。
第1部 電力会社のコーポレート・ガバナンス
1.原子力発電と電気料金
1-1 公益事業会社の財産権の制約と独占料金電力会社の経営の歴史的展開を概観してみよう。
①私有財産権の制約
米国においていわゆる公益事業会社の会社経営はどうなるのかが古くから議論されてきた。バーリーとドッドが企業の社会的責任について論争を行った(本書42-43頁参照)が、ドッドは、「会社経営者は誰に対して受託者であるか」という1932年の論文において、公益事業に関して次のように指摘していた(Merrick Dodd, For Whom Are Corporate Managers Trustees? 45 Harv L. Rev. 1145 1163〈1932年〉)。
すなわち、公益事業に用いられる私有財産は、限定的な意味においてのみ私有財産である。たとえば、鉄道事業は、適切なサービスを提供し、当局からの要求によりその便益を拡大させ、合理的な料金のみを請求し、そして一定の後援者に特権を付与することにより得られる利益の大きい新ビジネスが可能であってもすべての乗客を同一に扱うこととなる、と指摘していた。
広告の後にも続きます
つまり、公益事業会社は、私有財産権に制約を受けることとなり、株主利益の最大化の企業活動ができなくなる。
②電力会社の料金決定における株主利益の確保の憲法上の要請
電力事業の担い手はいろいろなものがあるようであるが、株主により所有される電力会社にあっては、電力事業の公共性は、規制等により株主に対する私有財産権の侵害ともなりうるが、そうだとすると憲法上株主に対して財産権を制約することの対価として適切な補償をなさねばならず、それが電力の認可料金の中で考慮されてきたようである。
米国の最高裁判所は、1898年から1944年まで憲法上のテイキングスの問題(takings clause)として料金決定の審査を行ってきたが、1944年のHope判決以降1987年までの間には、テイキングスの問題として憲法違反があると判決をしたものはなかったという(Richard Pierce, Public Utility Regulatory Takings:Should the Judiciary Attempt to police the Political Institutions? 77 Georgetown L. Rev. 2031〈1989年〉)。
つまり、わが国の憲法でも国民の私有財産権を認めているが、国はこれに制限を求めるときは、その財産権に対して補償をしなければならないという問題である。その補償額を料金決定においてどのように決めるのかが問題となる。
裁判所は、公益料金の決定が「公正価額」(fair value)に基づかなければならないと判示してきたし、当初の建設費用、社債および株式の市場価額、当初の建設費用と比較した現在の価額、法規定による特定料金の下で得られる財産の収益力等を考慮してケースごとに公正(just and right)でなければならないと判示していた(Smith v. Ames, 169 U.S. 466, 546〈1898年〉)。