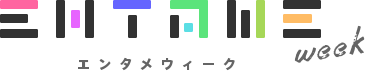はばたくために必要な力の一つに金融リテラシーがある。若年層向けの教育の必要性がますます高まっている状況だ。そこで、日本取引所グループの西の拠点である大阪取引所(大阪市)が行う、小学生親子向けの経済教室をのぞいてみた。

2024年3月、連携協定を結ぶ大阪府市との共催で行われた「春休み親子経済教室in北浜」。20組の定員が「1日で満席」になったということから、金融リテラシーへの関心の高まりが感じられる。今日のイベントのメインは、教育機関向けの教材として作られた株価の動きを体験するボードゲーム「ブルサ(bursa®)」。ゲームの開始に当たり、小学生にはなじみの薄い経済用語の解説から始まった。
■経済から見る社会の主人公
広告の後にも続きます
「私たちの社会の主人公は3者。政府と会社と家計。家計とは皆さんのおうちのこと」。
税金を使って社会を豊かにするのが「政府」だ。学校や病院、警察、消防、道路、図書館などを提供するために必要なモノやサービスを買い、公務員に賃金を払っている。「会社」はモノやサービスを売って利益を上げるところ。その利益から税金を納めることで社会を豊かにし、会社で働く人たちに賃金を払う。
では、家計の役割は?
「商品やサービスを買い、会社や公務員として働くと賃金をもらえる。賃金をもらうとそこから税金を払う。全体で見たら、モノやお金がぐるぐる回っている。このように、モノやお金が回る仕組みを経済といいます」。

株式売買ゲームで着目するのは、3者のうち「会社」だ。会社を作るにはまとまった「資金」がいる。その資金をどうやって工面するのか。会場からは「働いて貯めたお金を使う」との答え。だが、貯金だけでは大きなお金にならない。「銀行からお金を借りる」という手段もあるが、期日が来たら返金せねばならず、利息も発生する。そこで登場する秘密兵器が「株式でお金を集める」。今日のテーマだ。