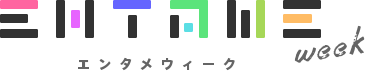さよならを言いそこねた人への手紙
この若い監督は、どうして、こんなすごい映画を作れたのだろう…と、心の底から驚き、長い時間、考え続けてみたのです。トルコのリゾートで、11歳の少女とその父親が休暇を過ごします。二人は普段は別々に暮らしていて、休暇だけを一緒に過ごす。抜けるような青空と、ずっと変わらぬであろう風景。その、光を浴びれば浴びるほど、その親子の過ごす刹那と、父親の抱える闇が際立ちます。と書くと、とてもシンプルな映画のように聞こえるのですが、構成は、とても複雑。過去と現在。それから、こうであったかもしれないという空想を、何度も行き来します。
まず、ひとりの女性。彼女は、子供の頃に撮ったビデオを見ながら、父親との休暇の思い出を回想しているようです。その父娘二人が、お互いに撮りあっているビデオ。ぶれてたり、とりあえず、テーブルに置いてあったり。でも、からかいあったり、ふさけあったり、ちょっとシリアスになったり、その時の、二人の親密さが生々しくうつってる。確かにそこに残されてる。
二人が一緒に長閑なリゾートで過ごす、そこで起こる、細々とした出来事。ここは普通の劇映画と同じ。歳が近くて、兄妹みたいな親子のアクションリアクション。11歳の彼女が父親に対して抱いている気持ちがよく伝わってきます。寄りが素晴らしくて、それぞれの表情の変化から目が離せません。兄のようなお父さんが大好きだけど、頼りなさに反発も覚える。お父さんがお金に困ってることだって知ってる。わたしは、もう、子供じゃない。父親は、そんな彼女を愛おしそうに見つめたり、困惑して、少し突き放したり…気持ちが寄り添ったり離れたりする、その二人の、なんともいえない心の距離感にハラハラします。

そして、父親が一人のとき。これは実は、大きくなった娘が記憶をつないで、当時の父親の像を結ぼうとしている。実際のお父さんではなく、多分、想像上のお父さん、なのでしょう。このつなぎのところが、大変に、効いています。とても悲しそうだったり、途方に暮れていたり。父親というより、人生のプレッシャーに苦しむ、一人の人間です。「今考えてみると、おそらく、こうであったであろう父」です。こうやって、娘が記憶の中の父親に、じりじりと近づいていく、その複雑な道程を映像と音でなぞっていく。
広告の後にも続きます
それに加えて、ここがこの映画の不思議なところなのですが、こうやって当時の父親と自分を思い出しながら、大人になった彼女の心の中だけで進行していく、無意識の何か。それが映画の中に不協和音のように入れ込まれます。稲妻のようにいきなり差し込む点滅する光の間で、ほのみえる何か、一瞬だけうつるノイズのように。その中で、女性が、あのときの父親と同じ年齢になって、レイブで、彼と、一緒に踊っていることが少しずつわかっていきます。そして最後には、このシーンが、すごい勢いで、他を飲み込んでいくのです。
明滅するライトの中で、子供だった自分と大人である父親、大人である自分と大人である父親、二人の間の時空を超えた複雑なカットバックに、父親の父親であり続けられなかった悲しみと娘の父親を失った悲しみが絡まり合うように、デヴィッド・ボウィとフレディー・マーキュリーが歌う『under pressure 』に重ねられていき、高まって、「this is our last dance, this is ourselves」という歌詞が反響しながら、少しずつ失われていくという場面では鳥肌が立ちました。大きくなった子供が、自分が子供だった頃の親を理解していく。それと同時に。失った親を、もう一度完全に失っていくような。
そうだったんだね、わたし、わかったよ、さよなら、さよなら、あのときの、おとうさん、あのときのわたし、という監督の声が、最後に、聞こえたような気がしました。
親と子は、親しい時間を共有するかもしれない。でも、どんな親子も、「宿命的に」すれ違うことを。すれ違っていたことを。必ず、私たちは大人になると理解をする瞬間があります。自分が無邪気であったときに、親は何に苦労していたのか。自分が寝た後、何を考えていたのか。実は何も知らない。親子というものは、ただ、ある一時期を大人と子供という異人として、「交差」するだけ。
その、「あっ」という目眩の瞬間を、この映画は、形にしてみせる。触れられぬものに、触れたようで、とても、こわかった。親の人生は、子供にとって、どのみちミステリアスで決して触れることはできない部分を持っている。でも、この映画のように、映像と音で、その距離を正確にはかってみせることは普通しない。だって、その断絶は、埋められないものだと、認めるしかなくなるから。激しい痛みを感じても、映画を作ることを通して、触れられぬものに触れにいく。どうしても、そうしなければいけない、という、この監督の思いが伝わってきて、苦しくてたまらなかった。