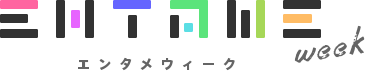『脱亜論』とは。いつ誰が書いたのか概要を簡単に解説
『脱亜論』が初めて世に出たのは、1885年3月16日のこと。福沢諭吉が創刊した新聞「時事新報」に掲載された無署名の社説という形でした。
この社説が福沢諭吉が書いたものだといわれるようになったのは、「時事新報」の主筆だった石河幹明が1933年に編集した『続福澤全集』に収録されたから。
福沢諭吉ではなく石河幹明が書いたものではないか、という説もありますが、石河が「時事新報」に入社したのは1885年4月で、さらに社説に関わるようになったのは1887年以降なので時期があいません。また仮に福沢諭吉が書いたものではなかったとしても、掲載にあたっては何かしらのかたちで関わっていたことは間違いないと考えられています。
「時事新報」は、日本で初めて漫画を掲載したり、料理のレシピを載せたりと画期的な紙面作りが人気で、戦前の「五大新聞」の一角を占めていました。そのため『脱亜論』を目にした読書も多かったと推測されますが、世に出た当初は無署名の社説にすぎず、長さも原稿用紙6枚分ほどしかなかったことから、まったくといっていいほど注目されなかったそうです。
『脱亜論』の内容を簡単に解説!差別を書いているわけではなかった
広告の後にも続きます
約2000文字の『脱亜論』。その内容は、2つの段落で構成されています。
第1段落で作者は、東洋に押し寄せてくる西洋文明を「麻疹のようなもの」と述べます。さらにこれを防ぐのではなく取り入れ、国民が適応するよう促すべきだとしました。その点で、明治維新を成し遂げた日本だけが、アジア的な古い価値観を抜け出し新たな一機軸を見出すことに成功したと評価しています。
第2段落では、そんな日本に比べて、西洋文明を拒絶し近代化に抵抗を続け、古い体制の維持に努める清や朝鮮を「不幸」だとし、明治維新のような改革がなされるならばまだしも、今のような状況が続けば数年で西洋列強諸国に国土を分割され、滅亡すると断言。そのような清や朝鮮と日本が、「アジア」という枠組みで一括りにされてしまうことは「一大不幸」であると危惧しています。
このように論じたうえで、隣国だからという理由で特別な関係を結ぶのではなく、欧米諸国と同様の付きあい方をし、日本は独自に近代化を進めることが望ましいと結論。「我れは心に於て亜細亜東方の悪友を謝絶するものなり」と結びました。
この『脱亜論』の内容は、その後の歴史や現在の情勢を鑑みて、実に先見の明があると評価されています。
2022年10月30日